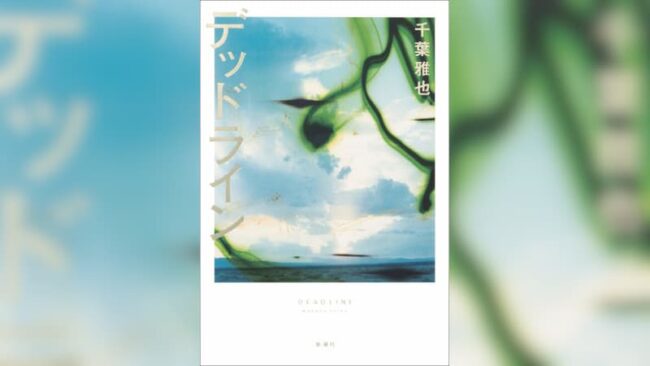章番号のないプロローグのような導入は男と男の性愛の場、映画では同性の恋愛ものも結構見ますが、ここでの描写は恋愛感情を抜きにしたいわゆる(有料)ハッテンバと言われる場所です。そこでの主人公の〇〇の行動を追う描写から始まります。

〇〇としたのは、実際にこの小説では大学院の修士課程に学ぶ一人称の「僕」が他者から呼ばれる場合には〇〇と記述されているからです。
そのことから何を読み取るかは読み手次第ということですが、主要な登場人物である他のふたりの表記も特徴的です。
ひとりは「浪人して一年遅れで僕と同じ大学に合格した」Kであり、そのKが「映画サークルに入るというので、サークルや部活を好まない僕も、小学生が連れションに行くみたいに一緒に入ることに」したとあり、そしてもうひとりは「同じ学科で同学年の」知子と言い、「一年のときからそのサークルにいた」女性です。
僕は「〇〇」、僕が好意を持っている同性の友人は「K」、そしてKに好意を持っており、僕が同性愛者であることをカミングアウトした女性は「知子」と記述されています。
この表記はかなり意図的と思われます。何を読み取るかは読み手次第と書きましたが難しいですね。おそらく後半になって明確になってくるこの小説のテーマ「動物になることと女性になることはどちらが重要か」を象徴しているのだと思います。
「K」≒「動物」、「知子」≒「女性」、そして「僕」≒ゲイである「〇〇」
読み始めてしばらくは戸惑います。その三人が主要な人物であることがわかるのはかなり後半であり、他にも何人かがほぼ同列に記述されて登場することもありますし、場面転換がかなり頻繁に起き、事象が断片的に記述されていきますのでなかなか全体像を把握するのが難しいです。
一応7章の章立てにはなっていますが、時間的にも明確にされているわけではないですし、視点は一貫して「僕」の一人称視点です。言うなれば日付のない日記のような感じです。
大学院修士課程に学ぶ「僕」が修士論文を書くまでの日々を軸に、「僕」の性愛恋愛事情、「K」とともに関わる映画制作の話、「知子」の失恋、そして後半になりますと父親の会社の倒産による経済事情などが綴られていきます。
ただどの問題にしても切迫感とか差し迫るものに対する心情のようなものが語られることはなく、どこか全てのことに対して膜が張ったような曖昧さが漂っています。それはこの小説のタイトルになっている修士論文の『デッドライン』が間近に迫り、また仮に期限に提出できなく、父親の破産によりスネがかじれなくなるかも知れないという状態を目の前にしてもさほど大きくは変わりません。
しかし、この小説が読ませるものになっているのは逆にそこであり、全体を覆うそうした茫漠とした雰囲気と修士論文に関連して語られる哲学的な話が妙にマッチして日記的と言えどもちょっとした青春物語になっているのです。
「僕」が最終的にたどり着く哲学的テーマは「動物になることと女性になることはどちらが重要か」というドゥルーズから導き出された何とも奇妙なテーマです。ただ、論文のテーマをドゥルーズにした経緯もかなり成り行きでというニュアンスで語られています。
そもそも「僕」が哲学の道に進んだのは、「高校時代からインテリっぽい言葉のカッコよさに憧れて」いたからで、大学では第二外国語にフランス語を選択し、「ドゥルーズやデリダ、フーコー、ラカンといったフランス現代思想の原書をなんとか拾い読みして一人前に研究活動をしているつもり」になっていただけで、四年生になってすぐの卒論のテーマ発表では「インターネット時代の新たなメディア論をドゥルーズらの思想を使って展開したい」と語ったら、学科長に「十年早い、研究になっとらん」と一蹴され「君みたいなのはね、もっと泥臭いものをやったらいいんだよ、モースの『贈与論』とか」をという優柔不断な「僕」です。
それ以上モースに関する記述はありませんが卒論はモースなのでしょう。「僕」によれば、マルセル・モースとは、レヴィ=ストロースを「構造主義」、ドゥルーズやデリダを「ポスト構造主義」と位置づければ、レヴィ=ストロースはモースの『贈与論』を整理継承しており、その意味ではフランス現代思想の祖父ということになるそうです。
で、修士論文の指導教員となるのが中国哲学が専門でフランス語やドイツ語も堪能でデリダに関する論文もある徳永先生です。この先生がなかなか味のある人で、『荘子』をテキストに使いながら「古代中国にはそもそもデリダ的な問いがあった」と『僕』に刺激を与えます。
で、修士論文のテーマを何にするかで一年くらいを費やし、それを見かねた徳永先生からの問いかけに「やはりモースでは難しいと思います」と答えますと「大物をやったほうがいいです」と振られ「ドゥルーズですか」と、我が意を得たりではあるのですが、その実主体性のなさをみせています。
この小説に独特なものが感じられるのは、こうしたぼんやりした青春時代特有の感覚の中で描かれる、ゲイである「僕」の性愛恋愛感情の描写からにじみ出る身体性の不確かさとドゥルーズから「僕」が導き出す哲学的思索が交錯していく点かと思います。
その哲学的思索部分だけ抜き出します。
『千のプラトー』第十章に「動物になること」が集中的に論じられているらしく、「芸術を通して人は動物になる」、つまり自由になるといったニュンアンスのことが書かれているそうです。
『千のプラトー』によれば、人間/動物という対立は、マジョリティ/マイノリティという対立を含意している。人間とは、支配的なマジョリティである。西洋の言語では、しばしば人間を表す単語は「男性」も意味する。人間の支配から逃れて動物になる。それがひとつ。そしてまた、男性の支配から逃れる「女性への生成変化」がある。それがもうひとつ。
人間=男性に対するマイノリティとしての、動物と女性。
(106p)
大学に入って一人暮らしを始め、実際に同性愛を生きるようになって、不安を感じるときは現代思想は助けになってくれた。世の中の「道徳」とは結局はマジョリティの価値観であり、マジョリティの支配を維持するための装置である。マイノリティは道徳に抵抗する存在だ。抵抗してよいのだ。いや、すべきなのだ。そういう励ましが、フランス現代思想のそこかしこから聞こえてきたのだった。
(107p)
「女性になりたいわけじゃない」
と、僕はカムアウトするたびに説明していた。知子にもそういったと思う。
僕は、男性をウケの立場から欲望するが、それは性同一性障害やトランスジェンダーとは別のことだ。僕は、男として男を欲望し、男に挿入される。
僕は、自分には欠けている「普通の男性性」に憧れていた。おそらくはその欠如感が、僕を動物というテーマへ導いている。動物になることを問う。それは僕にとっては、男とは何かを問うことなのだ。
(121p)
僕は女性になることをすでに遂げている気がする。物理的にメスになるのではなく、潜在的なプロセスとしての女性になること。僕の場合、潜在的に女性になっていて、動物的男性に愛されたいのだが、だがまた、僕自身がその動物的男性のようになりたい、という欲望がある…
(122p)
動物と女性、この二者の関係は自分にとっていかなる問題なのか。それ以上問い進めることを拒む透明な壁がある気がする。水槽に閉じ込められた魚のようだ。そこに壁があるとわからないままガラスに突進してしまう愚かな魚のように、僕は根本的な謎に突進している。
(123p)
ということで、結局「僕」は修士論文の『デッドライン』に間に合わず、この課題は修士3年目に持ち越し、また経済的にも変化があり、学費は実家が出してくれることにはなりますが、生活費は自分で工面することになり、奨学金にアルバイト、そして住まいもランクを落とし、車も手放すという環境変化が起きます。
そしてエピローグ、プロローグと同様に男と男の性愛の場と思われる発展場の描写で終わります。しかしそこは有料のハッテンバではなく「河川敷にある野球場のバックネットの裏の(略)プレハブの物置」です。