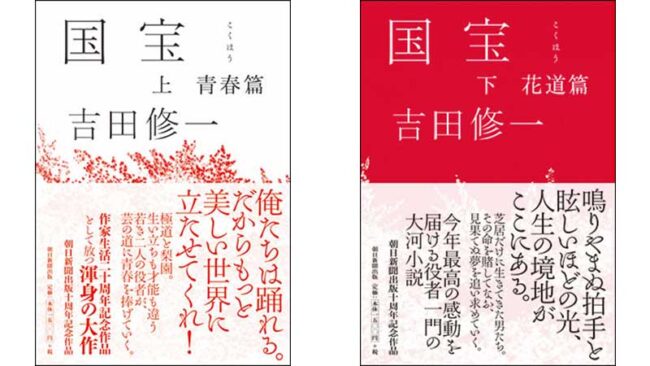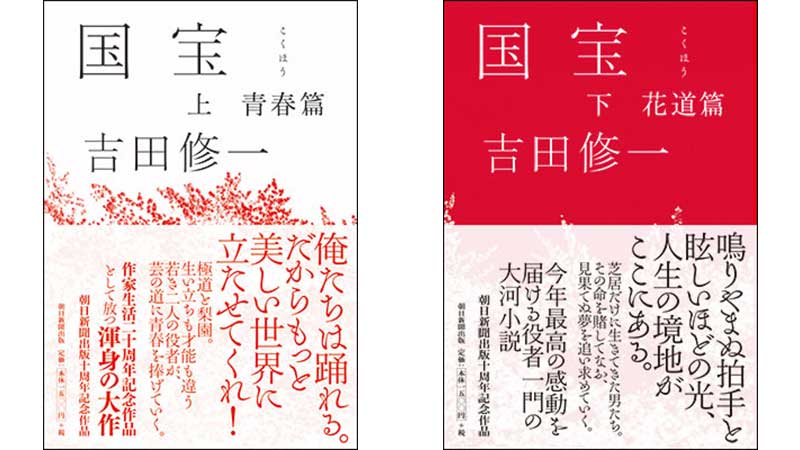
この『国宝』、昨年から今年の5月にかけて朝日新聞に連載された小説の単行本化とのことです。連載小説なんてかなりプレッシャーのかかる作業ではないかと思いますが、吉田修一さんの最近の作品はほとんどこのパターンですし、個人サイトを見てみても三本が連載中とあります。性に合っているんでしょうか。
というより、書き下ろしという出版スタイルが成立しにくくなっているのかも知れません。売れないという意味です。
連載小説というものを連載中に読んだことがないのですが、想像で言えば、おそらく一回あたり原稿用紙2,3枚程度だと思いますので、その中にもメリハリをつけ、次に興味をもたせることが重要になるのでしょうから、全体の重厚感とか、骨太感のようなものは若干犠牲になるのかもしれません。
この『国宝』を読んで最初に感じたことは、たとえて言うなら、連ドラスタイルの大河ドラマを見ているような感じと言いますか、なかなか一点に深く入り込んでいくものは感じられません。ふわふわした感じといいますか、すーと流れていってしまうような感じです。
ただ、無茶苦茶面白いですし、最後まですらすら読めてしまいます。
そのすらすら読めるというのがこの小説のポイントで、ひとことで言ってしまいますと、この小説は青春群像劇です。時間経過としては半世紀くらいの時間が流れるのですが、内容は一貫して青春の人間関係が描かれ、最後まで青春群像劇です。
悪人は誰も出てきません。吉田修一さんの小説の特徴なんですが、悪事は描かれても悪人は出てきません。皆、いいやつばかりです。
それだけに、読み終わっても、主人公の喜久雄でさえ人物像がはっきりしてきません。喜久雄が年を取っていく印象があまり感じられないのです。喜久雄だけではなく周りの人物皆そうなんですが、主要な人物はかなり早い段階に出揃い、それも皆15,6歳の年齢で登場し、その後、時代背景の描写もほとんどなく、あまり社会との関係も描かれず進みますので、その年齢のまま70歳(だったかな?)くらいまでいってしまうような印象です。
喜久雄は、長崎で羽振りを利かせるヤクザの家に生まれ、中学生にして背中に彫り物をしています。ある年の新年会、ヤクザの抗争により父親が殺され、家は没落します。喜久雄はその新年会の余興で部屋住みと徳次とともに歌舞伎舞踊を踊るのですが、それがたまたま居合わせた関西歌舞伎の花井半次郎の目にとまり、徳次とともに大阪に引き取られ歌舞伎役者としての修業に入ります。
ちょっと話はそれますが、吉田修一さんは長崎出身で、初期作品には長崎を舞台にしたものもあったと思いますし、その名の入った『長崎乱楽坂』なんてのは、この『国宝』の出だしの雰囲気のまま最後まで行く作品で、私の好きなもののひとつで、おお、昔に戻ったか!とほんのちょっと感動もし期待しました。別に裏切られたというわけではなくそれだけの話です(笑)。
その関連でちょっと書いておきますと、喜久雄の父親を殺したのはその子分の辻村で、なおかつその場を花井半次郎は見ていますので、これ、どこかで何かが起きるキーポイントだな、なおかつ喜久雄は辻村に金銭的に世話になるわけですから、楽しみ!と思って読んでいったんですが、半次郎は何も言わずに死んでしまい、辻村も最後の最後、喜久雄が国宝になるかならないかくらいの時に、実は…といって死んでいきました(笑)。
こういうところが連ドラ仕立ての大河小説って感じるところなんです。
物語の始まりは昭和39年、1964年、東京オリッピクが行われた年です。
で、舞台は長崎から大阪に移ります。花井半次郎には喜久雄と同い年の俊介がいます。歌舞伎の世界ですから跡継ぎです。この二人が競い合うように歌舞伎の修業を重ねていくのが中盤の軸になっています。二人ともに女形です。
喜久雄は、長崎にいたときに付き合っていた春江を大阪に呼びます。付き合っていたといっても、父親の死後しばらくは春江の家に入り浸りで、はっきりは書かれていませんが、春江に客を取らせていたようでもあります。
吉田修一さんの小説にはそうした男女関係のあれこれが出てくることはほとんどなく、さらりとしたもんで、この春江は後に俊介の妻として花井の家を支えていく女将になります。
喜久雄が歌舞伎役者として成長していくことを軸にして、その競争相手として俊介がおり、後にどん底まで落ちる俊介の妻として支えることになる春江、そして、最後まで喜久雄を坊っちゃんと呼んで支えることになる2歳年上の徳次、まとめてみれば、この4人の 50年、60年におよぶ青春群像劇ということになります。
もちろん他にも数多くの人物が登場し、あれこれ絡んでは来るのですが、登場時、これは重要人物かと思えても、その後ほとんど登場しなくなり、ある時、何年後かに、その子供が…といった感じでびっくリさせられたりします。
その代表人物が祇園の舞妓市駒で、俊介とともに祇園のお茶屋で遊んだ際に親しくなり、その帰り道、市駒が、
「喜久雄さん、祇園のお茶屋で遊んだの、今日が初めてどっしゃろ?」
「そやで」
「じゃあ、うち、決めたわ」
「決めたて、何をや?」
「うち、喜久雄さんにするわ」
と、自分の人生を喜久雄に賭けると言うのです。
これは、重要人物!って、誰でも思いますわね。でも、その後ほとんど出てきません(笑)。でも、いつの間にやら娘が生まれています。この娘、綾乃は、後半、あれこれ物語を作ってくれます。
他にも、歌舞伎の制作興行会社、まあ松竹みたいなもんでしょうが、そこのやり手の竹野、街のチンピラ(のような感じ)から売れっ子のお笑いタレントになる弁天、喜久雄の妻となる彰子、この人も突然出てきます(笑)。
そんなこんなで、正直、物語は深まりませんし、人物像も登場時に第一印象で感じたままあまり変わらず…、ああ、あらためて思い返してみますと一番変わっていくのは春江ですね。
長崎時代は、将来やばいよねというくらい先が思いやられる様な立場に置かれていたのが、大阪時代には、何も描かれないうちに(笑)自力で店を持つようなっていましたし、俊介が落ち込んで失踪する際におそらく一緒に来てくれとでも言われたのでしょうが、数年はどん底の生活を共にしていますし、俊介が歌舞伎の世界に戻ってからは、小説の描写自体もかなり多くなり、丹波屋(花井家)を背負って立つまでになっています。
その俊介が失踪したわけは、三代目花井半次郎の名を喜久雄が継ぐことになったからです。二人は競い合ってはいても共に相手を認め慕い合う仲として描かれており、二代目半次郎が、実の子ではなく喜久雄に三代目を継がせると決めたときにも、俊介は恨みつらみを言うことなく、しばらくして自ら消えてしまったわけです。言葉にはしなくてもそれだけショックだったということです。
数年の放浪の末、歌舞伎界に戻った俊介は、その苦労が芸に深みを与えたのか、人気役者となり名跡花井白虎の名を継ぎますが、放浪時の不摂生のせいで糖尿病を患い亡くなります。
徳次はと言えば、とにかくこの人物は任侠に生きる人物で、中頃まで、とにかく喜久雄のそばを離れず、大阪時代には春江と喜久雄の間を取り持ったり、市駒に綾乃が生まれてからは綾乃の父親代わりのように面倒をみたりしています。
ところがです、中盤から終盤にかけてのところで、突然、中国へ行ってしまいます。
はあ?って感じなんですが、これ、不思議なんですが、あまり気にならないんですね。そういう話だと思って読んでいるからからもしれませんが(笑)、いずれにしても吉田修一さんはこういうところうまいです。
で、徳次、これでいなくなったわけではありません。最後に登場します。中国で事業に成功し、ネット通販会社「白河集団公司」の社長となって戻ってきます。戻ってくるところで終わっています。
連ドラ仕立ての大河小説ですからまあいいでしょう(笑)。
肝心の喜久雄です。三代目半次郎を継いだものの、(なぜだったか忘れてしまいましたが)俊介の活躍と入れ替わるように、辛酸を舐めることになり、一切いい役をもらえなくなってしまうという憂き目にあいます。
それを支えるのが江戸歌舞伎の大御所(だったかな)吾妻千五郎の娘彰子です。この彰子、突然登場し、喜久雄と結婚することになるのですが、この件、喜久雄が損得勘定、つまり千五郎と親族になっていい役をもらおうとするという、なんとも喜久雄のキャラからしたら違和感のある設定で、ちょっと物語つくり過ぎじゃないと思います。
この小説に登場する女性たち、とにかく皆気丈でいい人ばかりです。彰子も、結婚を反対されながらも勘当同然で喜久雄についていき、後に喜久雄から騙していたと告白されても、騙すのなら最後まで騙してよと、喜久雄のもとを去るのではなく、マネージャーの立場で喜久雄を支えるのです。
まあ、全体的に男女関係はかなりクラシカルで、甘えん坊の男たちを陰で支える女たちといったところです。
で、喜久雄ですね。
喜久雄には歌舞伎のことしか見えていないようです。その芸は神の領域にも達しようかというところまでいきます。ただ、このあたりの描写にほとんど現実感はなく、宙をさまよっているような描き方です。たとえば、
「完璧を超えた完璧な芸。」
「完璧といいますのは、結局、人様の作り出した域でございます。」
「しかし、喜久雄の芸はその完璧を超えてしまった。この瞬間、完璧をも求める客には喜久雄が見えなくなり、同じように喜久雄には客が見えなくなってくるのではありませんでしょうか。」
などと表現され、喜久雄はすでにこの世ではないものを見ているということになり、まあ言っちゃなんですが、これは実際の舞台上のことでいえば、他の役者と噛み合っておらず、ダメな舞台ということになるわけで、言葉上のこととはいえ、現実の舞台や歌舞伎を適確にとらえているとは思えません。
実際、結末は、「阿古屋」を演じる喜久雄がすでに現実を見ておらず、舞台から客席へ下り、そのまま客席を抜け、さらに歌舞伎座を出て銀座の街へ出て「きれいだな」とつぶや(いたかに見える)くという、冷めた見方をすれば、芸に生きる者とすればちょっと違うんじゃないと言いたくなるようなラストなんでございます。
やはり、たとえ売れなくても、ここはこうした大作を書くのであれば、書き下ろしで書いていただきたく思いし、それに、そろそろ吉田修一さんも三代目半次郎の境地に達しているのではないかと思うわけです。
ということで、読み物としてはとても面白く、吉田修一さんの筆力が光る作品だとは思います。とにかく読ませる作家です。