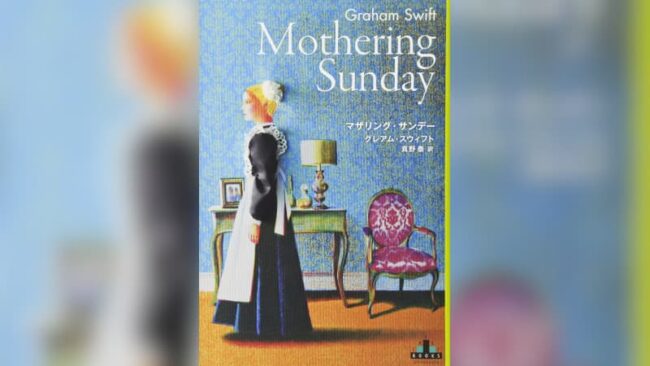この小説の映画化「帰らない日曜日」を見てどんな小説なんだろうと興味を持ち読んでみました。
小説と映画という表現形態の違いがはっきり出ています。ただ、ジェーンの人物像については小説を読んだ後でも映画のジェーンに違和感はありません。映画がよくできているということだと思います
映画と原作小説
映画を一人称視点で撮ることは不可能ではないと思いますが、仮に試みるにしても2時間程度の全編でその視点を保つことは難しいでしょう。それに私視点のつもりで撮ったとしてもそれは私という人物を追っているに過ぎなくなる可能性のほうが高く、小説のようなわけにはいきません。映画、つまりカメラは、基本第三者視点しか持ちえないということです。
この『マザリング・サンデー』は、ジェーン・フェアチャイルドという女性の見たもの、感じたこと、想像したことが、「ジェーンは」とか「彼女は」の表記で語られていく一人称視点の小説です。
ですので、映画にあったニヴン家など三家の食事会のシーンなどはジェーンの想像として書かれているに過ぎず、映画ではなかなか来ないポールを待つエマの不機嫌さが強調されますが、小説のジェーンの想像からそうしたエマの人物像が浮かんでくることはありません。あくまでも婚約者との待ち合わせに2時間も遅れて、ましてや自分とのセックスという時間を過ごし、なお慌てることなく、その様を見せつけるようにゆっくりと衣服を身に着けていくポールという人物を観察し、その延長線上でそのときポールを待っているだろうエマを想像するだけです。
映画で感じた「端から漂う不穏な空気」も小説にはまったくありません。そもそもジェーンがメイドとして働くニヴン家の主人も登場するのは夫の方だけで妻は登場しません。映画ではポールが亡くなった夜、ニヴン家の女主人がジェーンに、あなたは孤児だから生れた時から何も持っていなくて失うものがないわねと嗚咽しながら無神経極まりないことを言っていましたが、そうした描写もまったくありません。
それでもなお、映画は小説のジェーンをよくとらえていると感じます。映画のレビューでは「現代女性ジェーン」と書いていますが、1924年という時代や直接の主人ではないにしてもアッパークラスの男性と大人の関係にあるメイドという立場からすればなかなか自立した女性をイメージするのは難しく感じたことからのレビューということです。
ジェーン、観察し想像する
この小説の中のジェーンは自立した女性です。
1924年、22歳のジェーンはニヴン家のメイドとして働いていますが、その主人やそのとき大人の関係にある隣家のポールを見る目は観察の目です。ジェーンは常に相手の行動を観察し、なにゆえその行動をするのかを想像します。
それゆえジェーンは知的で自立した人物として立ち現れます。ニヴン家の主人との会話には、ジェーンがひとりの人間として尊重されている様子がうかがえますし、ポールはジェーンのことをジェイと呼び、僕の友達だと言います。
「帰らない日曜日」ではエヴァ・ユッソン監督が1世紀前の女性を現代女性としてよみがえらせたのかと思っていたジェーンは、実は原作のジェーンそのままだったということです。
映画でもそうでしたが、このジェーンとポールの間に恋愛を感じさせるところはありません。これはジェーンがポールを恋愛対象としてみているわけではなく、そもそもそうした関係が思い浮かぶ社会的関係がありえないということもあるにしても、それ以上にジェーンが22歳にしてすでに自分を客観的にとらえることができる人物だからということです。それゆえふたりが過ごすマザリング・サンデーの2時間あまりの描写において描かれるのはジェーンの内面や感情ではなくジェーンが見るポールであり、そこから派生してジェーンが想像するまさしくジェーンの小説世界だということです。
ジェーンは後にニヴン家のメイドを辞め、オックスフォードの書店に勤め、そして作家となっていきます。この小説にはその後作家となった40代くらいのジェーン、そしてジャーナリストか誰かのインタビューに答える70代か80代くらいのジェーンが登場します。ですので一見老年のジェーンの回想の物語にもみえますが、22歳のジェーンは今生きている人物として感じられるよう描かれています。
オックスフォード時代の記述はさほど多くなく、老年のジェーンがインタビューに答えるようなスタイルで語られますので回想のようにもみえますが、マザリング・サンデーのジェーンの記述にはそうしたところはなく、老年のジェーンもこれは誰にも話さないことと語っています。
学びの源は本
ジェーンは孤児として育っており、ポールたちのような教育を受けているわけではありません。当時のイギリスのメイドの識字率がどの程度かはわかりませんので、ジェーンが本に興味を持ち、ニヴン家の主人に図書室の本を読んでいいかと願い出ることの特異性がどうなのかははっきりしませんが、まあおそらくかなり特別なことなんでしょう。
映画ではジェーンがポールの影響から本(映画では文字)への興味を持ったように感じましたが、小説ではジェーンがポールから何らかの影響を受けたようには描かれておらず、ニヴン家の図書室に入った時に感じた知への興味が出発点となり、その後主人に図書室の本を読む許可を得て多くのことを学んでいきます。
その知への欲求は、ポールとの逢瀬の後、裸のままシェリンガム家の図書室をめぐるシーンでも強く感じられます。映画ではジェーンがポールの万年筆を自分のものにするシーンを入れて、それが小説家となる重要なきっかけのように描いていましたが、それは映画的処理として視覚的に見せていたということであり、小説ではもっと漠然としたポールと過ごしたマザリング・サンデーそのものがきっかけとなっているように描かれています。
60代後半作家の描く22歳の女性
この『マザリング・サンデー』の発行年は2016年、著者グレアム・スウィフト67歳の時の作品です。へぇ~、67歳のおじいちゃんがこのジェーンという女性を書きますかとの驚きもありますが、逆に言えば、であるからこその1世紀という時間を越えたジェーンが生れたんじゃないかと思います。
ジェーンは孤児として施設で育ち、ニヴン家のメイドとして10代の半ばくらいから(らしい)働き始めています。隣家、といってもなにせイギリスのアッパークラスが暮らす郊外のことですので自転車でも数分から10分くらいはかかるような隣ですが、そのシェリンガム家の23歳のポールと大人の関係を持っています。
3月30日、マザリング・サンデーのその日、主人夫婦に朝食の提供をしているそのとき、ポールから11時に表玄関に来るようにと電話があります。ジェーンは、落ち着いた声で、はい、奥様などと答え、尋ねる主人には間違い電話でしたと答えます。その落ち着きはこうしたことが今日初めてではないことやポールとの関係がすでに長く続いていることを示しています。
そして初めてシェリンガム家を訪れるジェーン、それも正面玄関からです。メイドの立場からは考えられないことです。そしてその邸宅の跡継ぎの寝室へ入り、つかの間の逢瀬です。セックスシーンの描写はありませんが、映画でも描かれていたようにかなり具体的なセックスの結果としてシーツについたシミのことが語られます。
映画のレビューでは外に出したからのシミと書きましたが、そうではなくジェーンの中から流れ出たことによるシミだったようです。また、種にこだわるポールの描写をポールの憂鬱と理解しましたが、小説にはそれもありません。ジェーンはポールの憂鬱を想像していません。
ジェーンにとってポールは理解できない存在です。ジェーンはポールのことを自分とは違う世界の人間、つまり労働者階級のジェーンにとってはポールは自分とは違う層の人物です。ジェーンは端からポールに自分への愛があるなどとは思っていません。友だちだと言われることはジェーンにとって自分が認められている存在であると感じる証だということです。
こうした女性を描けるのは60代後半の男性の視点があるからではないかと思います。性愛を越えた人間関係ですし、男の描き方に幻想がありません。さらに言えば、女性を描くにしても、こう見られたいという男の願望やこう見ているはずだという男の思い込みを描くのではなく、そもそもたとえ性愛関係があったとしても相手を理解することにはつながらず、あくまでも他人は理解できないものとして、それでもなお理解しようと想像するという、いわば老練であるがゆえに可能な観察という思考パターンを22歳の女性ジェーンに反映させたからこそ生れた作品ではないかと思います。