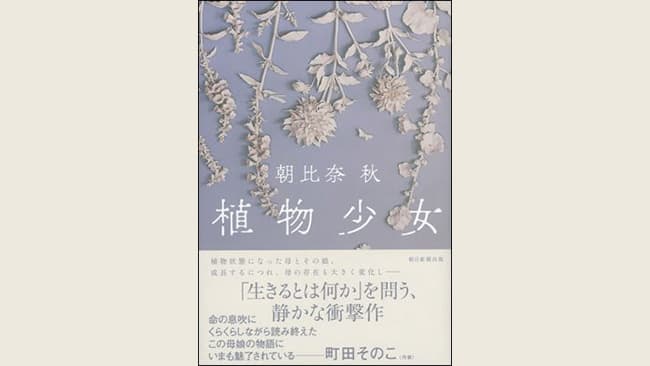今年2024年上半期の芥川賞は朝比奈秋さんの『サンショウウオの四十九日』と松永K三蔵さんの『バリ山行』の二作品が受賞されました。そのうちのおひとり朝比奈秋さんの『植物少女』です。『サンショウウオの四十九日』がデビュー5作目で、この『植物少女』が3作目です。昨年2023年の三島由紀夫賞を受賞しています。年2作くらいのペースで書かれていますね。
医師ゆえの視点が新鮮…
とてもおもしろい小説です。視点がユニークで新鮮ですし、作者の立ち位置に関心が向く作品です。また、他の作品が読みたくなる作家です。
1981年生ですので現在42、3歳、医師とのことです。専門は消化器内科で現在は勤務医ではないようです。専業作家になっていくのかもしれません。
この『植物少女』ではそうした医師という職業じゃないと持ち得ないような視点を感じます。「死」や「生」に対して客観的と言いますか、ちょっと引いたところから見ているような感じです。
美桜という女性とその母の話が三人称一元視点で書かれていきます。
書き出しもうまいです。美桜の母、深雪が亡くなり、その病院の霊安室から始まります。葬儀屋は美桜が生前長く母に付き添っていたと聞いているらしく母のことを尋ねます。美桜は「誰も生前の母をよく知らなくて」と答えます。
どういうことだろうと思いますよね。
さらに、その時の美桜の様子がちょっと変わっているのです。浮かれている感じなんです。悲しみからくる興奮状態ではなく、葬儀屋が困っているのを内心面白がり、父の困惑の表情をみて感慨(ここではどういう感慨かはわからない…)にふけるのです。
そして、霊柩車とともに病院を後にする時、車から流れる風景を眺めながら「わたしが母に会うために何千回も通った道」と言い、「風景が逆向きに流れていくと…」と続きます。
母親を相手の人形遊び…
本編に入り、「私にとって、母は会いに行く人物だった」と続きます。
こういうことです。美桜の母、深雪は美桜を生んだその日に脳出血を発症し意識を失い、そのまま植物人間となって病院で寝たきりになっているのです。ですので癌で亡くなるまでの26年間、美桜にとって母はいつも病院のベッドの上の人であり、母に会うために26年間、何千回と病院に通っていたということです。
本編は、時が「逆向きに流れていく」ように一気に20数年をさかのぼり、美桜の年齢に応じて、物心つく前の2、3歳と小学5年生のころで1章、高校生で1章、大学卒業後に役場に就職して1章、そして母が亡くって1章の4章で構成されています。
上に「植物状態で寝たきり」と書きましたが、ちょっと違うようです。脳死状態ですと自ら呼吸することも出来ませんが、植物状態というのは脳幹は働いていますので呼吸や咳をしたり、食べ物を咀嚼して飲み込むことはできるそうです。
この小説の中でも、美桜が2、3歳のころの描写として、美桜が母親の乳首に吸い付きますと乳が出るとありますし、小学生の時には美桜がクレパスを口紅のように母の唇に塗りますと食べ物と思いぺろぺろと舐めるとあります。
小学生の美桜は毎日家に帰るように病院に向かいます。裏口から入り、ボイラー室とリネン室を抜けスタッフオンリーの非常扉から病棟に入ります。スタッフも看護師も家族のようなものです。母に食事を与える際など不慣れな看護師にコツを教えたりします。
美桜が小学の時の母との関係は親密です。ただ、その親密さは一般的な母娘の関係とは逆転しています。言うなれば、幼い子が自らを母親に見立てて人形遊びをするような感じで、すでに書いたクレパスを口紅のように塗る行為もそのひとつです。また、父や祖母(母の母…)への不満を物言わぬ母に愚痴を語るようにぶつけたりします。
いわゆる人形遊びと違うのは、母には間違いなく血が通っており温かいのです。眠っていないときの母はベッドを起こして座った状態でいますので、母に寄り添い母の腕を自分の肩にまわして自分を抱かせた状態にして母の首元に顔をすりつけたりします。
この小学生の頃のパートはとても面白いですし、子どもの行動ですのではっとするようなこともあります。そうしたことがとてもうまく表現されています。母親の病室は5人部屋ですので他の患者とのこともありますし、医師ゆえの視点の記述などもあり、とにかくとても面白いです。
関西弁の会話体が多い小説ですので、読んだことはありませんがなんとなく知っている「じゃりン子チエ」が浮かんできます(単に関西弁を話すという意味程度です…)。
ベッドの上の母と写真の母…
美桜にとっては植物状態の母こそが母であり、父親や祖母の話の中の母、あるいは写真で見る母は姿形は母であっても、どこか違った存在に見えるようです。そのあたりの描写はあまり深くはありませんが、どことなく全体に漂っている父親との距離感というのはそうしたところからきているのでしょう。
父親が美桜に、
美桜がな、お母さんが生まれつき、こうなんや、って思ってしまうようにな、お父さんとか、おばあちゃんはどうしても、今のお母さんは深く寝てるだけやって思ってしまうんや
(65p)
とつぶやいて病室を去っていきます。美桜はすぐにこれまで何度もやってきたこと、持っている母の写真と眼の前の母を比べます。
そんなこと(特徴の全てが写真と一致すること)は、とうの昔に写真を片手に確認したことだった。その時はそれでも、女性と母が重なることはなかった。同じ女性だと確認したにもかかわらず、同一人物だとなぜか感じなかった。(略)
しかし、今やうっすらと写真の女性と母が繋がりはじめていた。急に母がいろんなものを失った人間に思えた。胸がぎゅっと苦しくなって、助けを求めるように母の横によっていったが、もたれることができなかった。
(66p)
そうやって少しずつ美桜と母との関係が変わっていきます。
物言わぬ母と青春の憂鬱…
美桜は高校生になっています。県を跨いだ高校に進学したため、「母は体調を崩して別居している」で通しており、親しい親友でさえ美桜の母を知るものはひとりもいません。
学校帰りに病院へ寄ることは変わっていません。看護師たちとの会話は関西ドラマによくある(かどうかはよく知らないけれど…)近所のおばちゃんおじちゃんとの会話のようです。
さすがに母親相手の人形遊びはしませんが、その延長線上のように、母の髪を茶に染めたり、金髪にしたり、ピアスをあけたりします。
このあたりの記述もとてもうまいです。母親をかまう行為に愛するがゆえに憎むといった感情が見え隠れするのです。髪の毛を染めたり、ピアスをあけたりするのもそのひとつですが、マカロンを食べさせ、その食べ方に「もうちょっと、上品に食べてよ」と言い、マカロンで母親をいじり、耳元で「脳なし」と囁きます。さらにマカロンをいくつも母の口に入れて吐けないように手で口を覆います。
母は何度もおえっと口を開くが、わたしは左手で母の後頭部を抑えて、右手で口を完全に密封した。母の目から涙が流れ落ちるのと同時にわたしの目からも涙がこぼれていった。
(84p)
この一連の行為には学校の部活での鬱屈した気持ちを母にぶつけているという面もありますが、人が成長していく過程で自分に一番近い人が憎くなるという感情でもあります。そのマカロンは親友の母親から家族で食べてねってもらったものなんです。
思春期の憂鬱もうまく書かれています。美桜は部活で陸上(多分短距離…)をやっています。先輩たちとうまくいっていないらしくそのモヤモヤや、父と祖母が語る母親が自分が知る母親と違うこと、つまり、自分は母と言葉をかわすことも母と並んで歩くこともできないということが眼の前に突き付けられるというそうした鬱屈した気持ちを走ることにぶつけているということだと思います。
夜、その悶々とした気持ちを吹っ切ろうとするかのように窓から外へ出てひとり走るシーンがあります。ただ、これがもひとつなんですね(ゴメン…)。悶々とした気持ちは伝わってくるのですが、そこから何かがクリアになる瞬間の描写がはっきりしていないんです。
ぶっ倒れるまで走って息があがり倒れ込みながら、実は母は今の自分と同じ充実した今を生きているのではないかと気づき、
母はかわいそうじゃない
みじめじゃない
空っぽなんかじゃない
(108p)
と、自分が成長するとともにできてきた母との隙間を必死に埋めようとする美桜がいます。
母のように、何も考えず何も思わず、呼吸だけをしていたい。
植物のように瑞々しく生きてみたい。
しかし、胸の中には一層苦しさが渦巻いていく。
(110p)
前後の流れはあまりよくないのですが、美桜の気持ち、あるいは作者の若干の本音が入っているかもしれない感情が溢れ出ています。
あそこは生きてる人だけやからなぁ…
大学を卒業し、隣町の役場に勤め始めてからは、病院に通う頻度がめっきり減ります。美桜は25歳になっており、結婚もし、お腹に子どももいます。母が今の状態になった年齢と同じになっています。そして母には癌が見つかっています。
美桜は出産の時、奇妙な感覚にとらわれたと親しい看護師に話します。
わたしな、出産する時にな、なんていったらいいんやろ。陣痛の一番ピークの時に、あまりに痛すぎて頭がぼんやりしてきて、そっから、なんも、考えられへんし、何も思わんくて、あと痛みも気にならなくなって
(略)
わたしな、植物状態なったんかもって
(略)
それでな、そっから、痛みが引いてもその感覚がずっと抜けんかってんけど、遥香(娘の名前…)が生まれてきて、大声で泣いた瞬間な、ハッとなって戻ってこれてん。これって、どっかでお母さんのこと気にしてたんかな
(131p)
そして祖母が亡くなり、その四十九日をひかえたある日の夜、祖母の骨壷を眺めていた美桜は突然思い立ったように祖母の骨壷を持って母の病院に駆けつけます。祖母の骨片を母の頬にこすりつけ、「わかる? おばあちゃん」と言いますと、母は唇を開けて骨片を舐めだします。
そして一年後、母は祖母の一周忌の少し前に亡くなります。
その日が友引であったことから、遺体は一旦病院から自宅へ移すことになります。美桜は母親に「あそこのほうがよかった?」と話しかけ、どこか寂しげに見える母を見つめながら「あそこは生きてる人だけやからなぁ」とつぶやきます。
こういうふうにみられる感覚を新鮮に感じます。
さらに、美桜は親戚へ葬儀の連絡をするわけですが、知らせを受けた皆が皆戸惑います。そして思います、この人たちにとって母はすでに死んでいる人だったのだと。
葬儀の早朝、美桜は棺にうつ伏して寝入ってしまい、母親と一体となった自分を感じます。
ただ、この場面、もっとも文学的表現が求められるところだと思いますが、残念ながらもうひとつ拡がりがありません。「全身に力をこめてみたが、腕も足もまったく反応しない」とか、「歯を食いしばりながら、瞼を開けようとした」といった具体的な体の反応が続くものの、なかなかそれが視覚イメージとして拡がりません。そして、
すると視界が、視界の裏にある何かが膨らんでは縮んでを繰り返している。そのリズムは間違いなく母のものだった。
(165p)
と、美桜は母との一体感を感じます。
で、終わるわけではなく、その後も、集まった親戚たちが美桜の知らない母親像、つまり美桜が生まれる前の物言い行動する母親の様子を語ったりすることや、自分の娘のことや、父親が長く付き合っている女性と別れると言い出すことや、母親の隣のベッドで同じく植物状態で入院していた美桜と同年代のあっ君とその母親が弔問に来たりして、最後の一文は
彼らは(母と同じ病室の人たちのこと…)今もあそこで座って呼吸を続けている。そのことを思い出すと、わたしは目を閉じて一息一息呼吸する。すると、自分もまた呼吸をして生きていることが実感されるのだった。
(178p)
と終わります。
文学的表現において物足りないところもありますが、とにかく視点が新鮮であることに惹きつけられ一気に読み切れます。芥川賞受賞作も含め他の作品も読んでみようと思います。