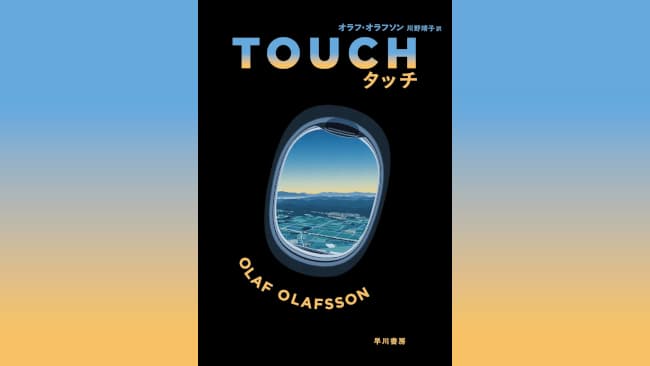今年2025年の1月に一般公開された映画「TOUCH/タッチ」の原作本です。被爆者についてちょっと気になるところがありましたので原作を読んでみました。
著者オラフ・オラフソンさん
映画のレビューにも書いていますが、著者のオラフ・オラフソンさんは1990年代にソニーでプレイステーションの開発を主導した経済人でもあり、作家としてはちょっと変わった経歴の持ち主です。
この原作本の最後に朱位昌併(あかくらしょうへい)さんという、肩書はアイスランド文学研究となっている方の解説文があるのですが、そこにもオラフソンさんのビジネスキャリアについて詳しく書かれています。
一九六二年にアイスランドの首都レイキャヴィークで生まれ、地元レイキャヴィーク高等学校を非常に優秀な成績で卒業後、オラフソンはアメリカのブランダイス大学で物理学を学ぶ。一九八五年に卒業すると、翌年ソニー・アメリカに入社し、ニューヨークを拠点とするソニー・インタラクティブ・エンタテインメントの最高経営責任者と社長を務め、家庭用ゲーム機プレイステーションの世界展開の仕掛け人でもあった彼は、八十年代と九十年代には、何度も日本を訪れて仕事をしている。やがて、プレイステーションの価格を上げるべきと主張する上層部と衝突し、値付けについてはオラフソンの主張が通ったものの、一九九六年にソニーを去る ことになる。その後は、タイム・ワーナーの上級副社長を務めるなど華々しい経歴を歩み、二〇一八年にAT&Tへのタイム・ワーナー売却手続きが完了後、ビジネスの世界を引退した。現在は執筆業に専念している。
(TOUCH/タッチ)
アイスランドとニューヨークを行ったり来たりというようなことも書かれており、どちらにも住まいがあるのでしょう。ただ、この『TOUCH/タッチ』は COVID-19 のパンデミック中にアイスランドで書かれたようです。
表現手段としての小説と映画の違い…
原作を読みますと、小説と映画の違いを強く感じます。映画のレビューはこちらです。
このことは映画化された小説については必ず思うことであり、特に小説が一人称小説である場合は顕著であり、つまるところ映画は第三者視点でしか表現できないものということにつきます。
物語という点では映画はかなり忠実に原作を踏襲しています。しかし、主人公であるクリストファーの強い思いはほとんど表現できていません。
解説を書いている朱位さんも映画に対して同じようなことを感じているようです。こんなことを書いています。
クリストファーとミコに焦点を当てた映画版について、オラフソンは好意的に「これはバルタサル・コルマウクルの作品だ」と評した。これに首肯できるのは、脚本製作におけるオラフ ソンの役割がどれほどだったかは定かでないものの、やはり小説と脚本は別物であり、映像となると言わずもがなであったからだ。ちなみに監督は製作中、「主演俳優であるエイイトル・オウラヴソン(Egill Ólafsson)に役を合わせるだけでなく、役にエイイトルを合わせることになるだろう」と語っていた。もし映画は観たが本書は未読だという方がいるならば、ぜひとも小説版を読んでほしい。 クリストファーの一人称で語られることでしか描かれないものが、本書には確かにあるのだから。
(TOUCH/タッチ)
朱位さんは「言わずもがな」というかなり強い言葉を使っていますが、とにかく映画は物語の説明に終わっておりあっさりした印象であることは間違いないです。
一人称小説を映画化する場合はあまり物語に囚われていはいけないということです。当然ですが一人称小説は主人公の内省的なものですので、主人公の思いを映像化するシーンを増やさないとなかなか小説の深さにはたどり着けないということじゃないかと思います。
原作にあって映画に足らぬもの…
物語は映画のレビューの「クリストファー、ミコに一目惚れ…」から読んでいただければほぼ原作と同じです。映画ではクリストファーは現在のミコの居場所を知りませんが、原作ではレイキャビクで暮らすクリストファーの Facebook にミコから「わたしの名前はミコ・ナカムラ、旧姓タカハシ。あなたは一九六九年にロンドンに住んでいたクリストファー・ハンネソンですか?」とメッセージが入るところから始まります。
もうひとつ大きく異なるのは、ラストシーン、映画ではふたりの息子が実際に登場しますが、原作ではその店に向かうところで終わっています。
原作は一人称小説ですので、当然クリストファーのミコへの思いがとても強く出ています。これを映像で表現するのはとても難しいです。たとえば 1969年の出会いのシーンにしても映画にはあまり工夫がありません。現実の出会いというのはあんなものだとは思いますが、なにせこの話は50年を経てもお互いに思い合っている二人ですし、映画ではほとんど語られていませんが、クリストファーはその後インガという女性と結婚してはいるもののミコへの思いを隠していなかったらしく、すでに亡くなっているインガへの自責の気持ちも書かれたりしているのです。
広島での再会のシーンも原作ではクリストファーはミコのアパートの下で不安を抱えながら何日も待ってやっと会う流れになっており、また会ってからの会話にしても50年前のミコとの連続性が感じられるものになっています。
さすがに奈良橋陽子さんのミコにはちょっと無理があります。俳優でもない奈良橋さんに求めることが無理とも言えますが、50年の淀みがなく率直なところ拍子抜けではあります。
また、1969年のミコを演じている Kōki, さん、今後どう成長していくのかはわかりませんがちょっと力不足の感は拭えません。一言で言えば影がないということかと思います。
やはり追想のラブストーリー…
という小説と映画の違いを感じたわけですが、そもそも原作を読もうと思った理由である被爆者のことについては、やはり映画はうまく表現されていません。
原作ではオラフソンさんの率直な気持ちがそのまま現れています。
クリストファーはミコと出会い、ミコから自分は被爆者だと告げられたときでもその言葉を知りません。その後クリストファーは何日も図書館に通い原爆投下や被爆者について自ら調べます。映画ではそうしたシーンはなく、代わりにミコが原爆の絵を何枚か見せることで表現しています。こうした描写の差というのはかなり大きいと思います。
朱位さんの解説によれば、オラフソンさんがなぜこの小説のプロットに被爆者を取り入れたかについて本人からこのように聞いたということを書いています。
オラフソンさんがソニーで働いていた30年くらい前のこと、日本人の同僚から打ち明け話をされたそうです。その同僚は自分の両親は広島出身で被爆者であると言い、そのことは周りの誰かに話したことはなく打ち明けられるはずもないと語ったということです。オラフソンさんはそれまで被爆者という存在を知らなかったらしく、このことを契機にして被爆者に対する誤解とそれにもとづく差別と偏見、そして被爆者が 感じてきた恥辱や無念を知ったということです。
映画はもちろんのこと原作でも基本はラブストーリーですのでさほど深い意味で被爆者というものを取り上げているわけではありません。ただ、原作を読みますと映画では抜け落ちてしまっている部分に気づくことがあります。
映画では、なぜミコと高橋が突然姿を消してしまったかについて心にストンと落ちる感じはありません。
ミコとタカハシは、ある日突然、誰にも告げずに店を閉めてまで姿を消してしまうのです。余程のことがなければそんなことはしないわけですから、タカハシには余程のことが起きたわけです。もちろん第一義的にはミコの妊娠ですが、いくらなんでもそれだけでこれまで築いてきたものすべて捨てて失踪してしまうなんてことは考えられません。
タカハシの思い込みです。タカハシは誤解にもとづく偏見を正しいものとして思い込んでしまっているのです。今の言葉で言えば陰謀論に陥ってしまっている状態ということです。被爆した者は必ず何らかの障害を発症する、仮に今でなくてもいずれそうなる、遺伝子異常、染色体異常で奇形障害を発症すると思いこんでしまっているのです。
映画ではあまり明確になっていなかったように思いますが、タカハシがミコを連れて産婦人医の元を訪れたのはミコに避妊手術をさせるためだったのです。結局そこで妊娠がわかりタカハシは姿を消すことを決断したわけで、率直言えば、原作にしてもタカハシの決断に不可解さは感じるのですが、それでもタカハシの強迫観念的思い込みは一定程度記述されていますのでそういうこともあるだろう程度には理解できます。
おそらく映画でも再会後の会話でそうしたことは語られていたんだと思いますが、小説では言葉で強く伝わることでも映像表現である映画ではそれを伝えたいと思うなら何らかの映像表現が必要ということです。
ということで、映画で気になっていた被爆者、あるいはその子どもに対する偏見について、原作には少なくとも言葉で明確に否定はされています。ただ、原作にしてもクリストファーの追憶が基本的なテーマですので被爆者、あるいは原爆への深い思慮のようなものが感じられることはありません。
実際、タカハシの思い込みはともかくとしてもミコがどう思っていたかもはっきりしていませんし、タカハシにしてもミコにしても出産の決断についての記述もありませんし、さらに言えばなぜ生まれた子を里子に出したかも実に不可解です。
やはり原作にしても追想のラブストーリーという小説でした。