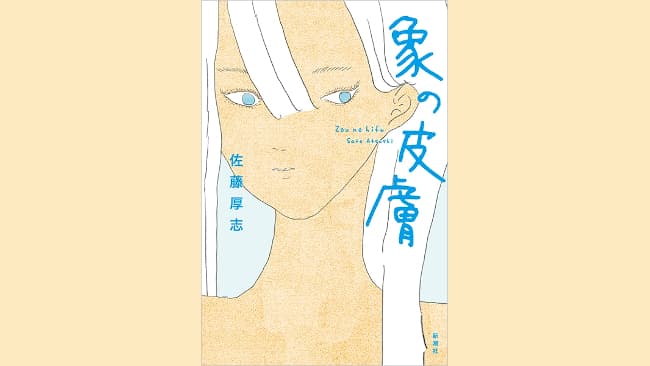2022年下半期の芥川賞は井戸川射子さんの『この世の喜びよ』と佐藤厚志さんの『荒地の家族』でした。その佐藤厚志さんの単行本化第一作の『象の皮膚」です。面白かったです。
井戸川射子著『この世の喜びよ』
その前に、芥川賞受賞作の井戸川射子さんの『この世の喜び」ですが、実は、読み始めてはみたものの挫折です。二度の挑戦に二度とも数ページあたりから先に進めません。
どうしてもその文体に気持ちがついていきません。こんな風に始まります。
あなたは積まれた山の中から、片手に握っているものとちょうど同じようなのを探した。豊作でしたのでどうぞ、という文字と、柚子に顔を描いたようなイラストが添えられた紙が貼ってある。その前の机に積まれた大量の柚子が、マスク越しでも目が開かれるようなにおいを放ち続ける。あなたは努めて、左右均等の力を両足にかけて立つ。片方に重心をかけると体が歪んでしまうと知ってからは、脚を組んで座ることもしない、腕時計も毎日左右交互につける。あなたは人が見ていないことを確認しつつ片手に一つずつ握っていき、大きさ重さを感じながら微調整し、ちょうどいい二つをようやく揃えた。喪服の生地は伸びにくいので、スカートの両側についたポケットにそれぞれ滑り込ませると、柚子の大きさで布は幕を張り膨らむ。
読んでいてもなかなか情景を思い浮かべることが出来ません。この「あなた」を「わたし」と置き換えて読みますと幾分イメージしやすくなります。つまり、一人称記述なのに主語が「あなた」になっている文章ということです。「わたし」の一人称記述で書いた文章を「あなた」に全文置き換えしたような文章ということです。
主語がはっきりしない文章が続きますので、これが挫折の一番の理由でしょう。
句読点も一般的ではありません。「脚を組んで座ることもしない、」この文末なら句点が普通なんですが読点で続いています。おそらく「脚を組んで座ることもしないし、」というニュアンスだと思いますが、読み手としてはどうしてもそこで意識が切れますのでとても読みにくいです。
こうしたことは作家の特徴ですので否定はしませんし、この文体がどう生かされているのか興味はありますので、一旦は挫折のままにしておき(笑)またいずれ再挑戦です。
佐藤厚志著『象の皮膚』
ということで、佐藤厚志さんの『象の皮膚』です。
アトピー性皮膚炎に苦しむ女性の物語です。ただ、その苦しさが書かれているわけではありません。むしろ語り口は淡白で軽妙さもありますので「かゆさ」は伝わってきますが「つらさ」はあまり伝わってきません。本人の体験もあるのかなあと思うもののアトピーに苦しむ人にはどう感じられるんだろうと若干心配にはなります。
小学校時代と20代になり契約社員として大型書店で働く2つの時間軸で語られていきます。小学校時代はアトピーのために「カビ」と呼ばれていじめられ、本人は身を隠すように生きてきたと語られます。悲壮感を感じさせる内容ではありません。
小学校時代の記述はすべてアトピーに関することですが、書店員の方は、同僚たちや特徴的な客の観察記述や万引き犯を捕まえたりイベントに客が殺到して大混乱になったりする話が中心になっています。書店での話は体験にもとづく点もあるとは思いますがかなり誇張されている印象です。東日本大震災に被災するシーンがあり、これは実体験と思われ現実感があります。
佐藤厚志さんは実際に仙台の丸善ジュンク堂書店で働いているそうです。芥川賞受賞作の『荒地の家族』も仙台近郊の町を舞台にし、東日本大震災によって多くのものを失っていく男の話とのことです。
観察眼視点が面白みを…
この一冊を読む限りでは観察眼的なものの見方をする方に感じます。三人称視点で語られていくということもありますが、主人公の凛でさえその内面記述はほとんどなくあっさりしたものです。それがアトピーの「つらさ」ではなく「かゆさ」の方がより伝わってくることにつながっているようです。
小学校の健康診断のシーンから始まり、医師から「これはカビです」と言われます。もちろん実際はアトピーです。こうしたところからも面白み(これは小説なので…)が生まれます。ただ、凛本人は、みなにカビと言われて、
(略)やっぱりわたしはカビだったんだ。そう思うと、自分だけが薄汚れていて皆に迷惑をかけていると感じた。学校生活はほんの数日で死んだ。どの日もかけがえのないものではなく、同じ日だった。
(7p)
学校生活が「同じ日だった」という言葉に苦しさのすべてが凝縮されています。
さらに、これ笑っちゃいけないのですが、家族がひどいんです。凛は幼いうちから親兄弟から「アトピー」とか「ピーコ」と呼ばれたといいます。親からもです。「父は」とか「母は」の表記がふっと「政夫は」と「真奈は」に変わったりします。
面白みを出すのがうまいですね。
それにしてもひどい家族です。政夫はアトピーについて「お前は気合が足りない」で済ませます。子どもの頃の話は学校での話がほとんどですので家族の記述は少ないのですが、母親も含めてまるで優しさというものがありません。いや、優しさというよりもそもそもアトピーに対する理解がまったくありません。それでもこんな家族でこんないい子(書店員のシーンから…)に育ったものだと思います。まあ、小説なんですけどね(笑)。
面白みのその先に…
子どもの頃の記述は、小学、中学、そして高校時代と、客観的に見ればいじめが続く「同じ日」の様子が描かれます。特に高校時代の教師のパワハラはひどいんです。ただ何度も言いますが、その「ひどさ」や「悲惨さ」は伝わってきません。
小説ですので別にどう書いてもいいのですが、こういう書き方ができることに不思議な感じがします。ひどいことやその悪意を書いているわけではないのですが、客観的に見ればそれはダメだろうということが淡々と書かれているということです。
とにかく、子どもの頃の話は2割程度でそれ以外は書店員としての職場の話です。
面白みが意識されているのか、職業柄の観察眼が面白みを生み出すのかはわかりませんが面白いです。登場する人物は、同僚も客も奇異な人物が多いです。
書店員の最初のシーンが万引き犯を捕まえる話ですし、仲間内で「油男」と呼んでいる、女性スタッフに成人向けコミックのタイトルを読み上げさせる男や、おそらく金券ショップで買ったであろう図書カードで本を買い、それを返品して換金する(わずかな差額のため?)女や、どこで買ったかわからないボロボロの本をここで買ったと言い張って返品しようとする男や、レジに並ぶ列に執拗に割り込もうとする女など、おそらくこういう客が本当にいるのでしょう。
同僚たちの登場人物はたくさんいますが、全体として強くこだわって書かれている人物はいません。40人くらいが働く大型店です。その中でも記述が目立つのは津田という新しく入ってきた男性と白銀という女性です。
津田はモテ男タイプなんでしょうか、独身の女性スタッフたちがそわそわし始めたと書いています。そしてどうやら二人ほどと関係を持ったらしく、ある日、凛を飲みに誘います。凛はわかっていながら誘いに乗ります。そして津田は二軒目に行こうと言い、断る凛に、じゃあうちで飲む? と畳み掛けてきます。りんはそれにも乗ります。結局、そこに付き合っているらしい同僚がやって来て、津田はすべて凛のせいにして言い訳をしまくります。
このシーンでも凛の内面は一切書かれませんのでどういう心理かわかりませんが、津田が凛にアトピー?と尋ね、見せてと言います。
凛は身をわずかに引いた。それは全くの拒否を示したというのではなかった。箇所によっては皮膚を見せてもよいと考えた。凛は皮膚を晒されることを警戒して、できる限り皮膚の話題を避けて生きてきて、他人の視線や注意をいくらかでも自分から遠ざけることに腐心してきた。終始自分の皮膚の状態や人の目が気になって、皮膚が人生の多くを占めてしまっていた。皮膚が自分自身だった。皮膚の苦しみを知ってもらうことは自分を知ってもらうことだった。誰にも知られないのは辛かった。いつからか視線を逃れたいという自然な感情と皮膚をあらわにしてみたいという隠れた欲求が相反して現れ出していた。
(112p)
作者はこれを書きたかったんでしょう。これがラストシーンに結びついていきます。
その前にもうひとりの白銀ですが、漫画やアニメオタクのような人物です。凛にはスマホアプリのシミュレーションゲームの中にソウイチという恋人がいます。凛の人物像としてはそれ以外にオタク(といっていいのかよくわからないが…)っぽい記述はありませんので、後にある声優のイベントのシーンのために登場させてある人物なんだろうと思います。
という感じで、書店員としての日常の中のちょっと奇異な人たちが並列に何人か書かれていくという感じです。記述のボリュームとしては震災による職場の混乱と一定程度復旧した後になぜか書店に人が溢れる状態やタレントの握手会に想定以上の人が集まり大混乱になる様子が多くを占めています。
ということでとても面白く感じますが、全体としては軸が曖昧すぎる、つまり、この後書きますが、ラストシーンに持っていくための積み重ねのようなものが足りない小説ではあります。
唐突感のあるラストシーンは…
凛は子どもの頃に象を見て、「硬くごわごわした象の皮膚は私の皮膚に似ている」と思い、「私は象の同類だ」と感じます。それがこの小説のタイトルになっているのですが、書店員時代の話のなかには本人がそのかゆさに苦しむ記述はあっても他者からの視点である「象の皮膚」という印象を受ける記述がありません。唯一津田とのシーンにあるだけです。
そしてラストシーン、かなり唐突に
鬱蒼と樹木の茂る公園内は風がなく、生暖かい空気が湿り気を帯びて停滞していた。
(134p)
と、それまではほとんどなかった情景描写から入り、深夜二時に「凛は夢遊病者のように背を丸めた姿勢で、公園の散歩コースを歩いて」います。眠ろうとしていたのにかゆさに耐えかねて部屋を出てきたのです。
そして凜はスニーカーを脱ぎ、Tシャツとジーンズを脱ぎ、素っ裸になります。下着はつけずに直接ジーンズをはいてきています。凛は走り始めます。
凛は地上を離れて空中に飛び立つ感覚を感じます。
と、本来ならここで凛の開放感が熱く語られなければいけない(と思うのは読者の勝手な望みだが…)のですが、残念ながらそうはなりません。あくまでも凜は自分の目に入ってくるものを観察します。凛は公園を俯瞰します。
わずかに
吹く風が、かさかさに乾いて敏感になった乳首を撫でた。恍惚があった。子宮が下がる感覚があった。
(118p)
とある程度です。
この『象の皮膚』の時点ではそうした人間の内面的な記述を得意とする作家ではないということだと思います。この点、芥川賞受賞作の『荒地の家族』がどうなっているのか楽しみです。
なおこの小説は2021年の三島由紀夫賞の候補になっています。