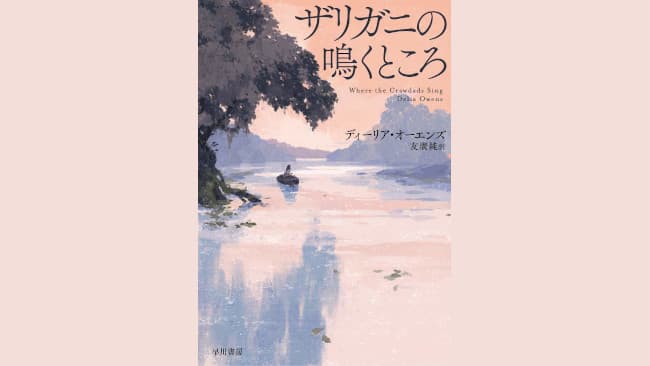昨年2022年の11月、この小説が原作の映画を見て興味を持ち、翻訳ものは好んで読むことはないのですが頑張りました。500ページの厚さ3cmもあるかという本です。
- 映画は原作にかなり忠実
- ノースカロライナの沼地1969年
- 湿地の少女カイア6歳1952年
- 湿地の生活と少年テイト
- チェイスとの恋、なのだが…
- テイトとの再会と湿地研究者(のようなもの)への道
- 逮捕、裁判、そして…
- 物語小説として読めば面白い
映画は原作にかなり忠実
驚くくらい映画は原作に忠実に作られていました。
日本の脚本家なんて原作のテーマや人物像を自分の思うように勝手に変えてしまうんですが(笑)、映画「ザリガニの鳴くところ」の脚本ルーシー・アリバーさんは原作のテーマも人物像もしっかり守り、ドラマとしても若干手を加えるだけで作者の意図するものを適確に伝えようとしていたことがわかります。
上の日本の…云々は「佐藤泰志著『夜、鳥たちが啼く』感想・レビュー・書評・ネタバレ」のことです。濱口竜介監督の「ドライブ・マイ・カー」もどちらかというとそうですね。
アメリカの場合、映画のスタッフにはそれぞれに組合があり、きちんと立場も守られていますので(現実は知らないけど…)職業意識も高いのかも知れません。それにおそらく原作者との契約も明確になっているのでしょう。
ノースカロライナの沼地1969年
湿地の少女(The Marsh Girl)と差別的意味を込めて呼ばれる少女カイアの6歳から23歳くらいまでが描かれ、そして最後の章では64歳で亡くなる1場面のある物語です。映画のレビューにも書きましたように内容はサバイバル&恋愛&リーガルドラマです。サスペンス要素とラブロマンス要素をあわせ持っている小説で、翻訳ではあまり実感として感じられるわけではありませんが「孤独」というものが一貫して語られていきます。
作者のディーリア・オーエンズさんは動物学者であり、専門雑誌への寄稿やアフリカで暮らしていたころの回顧録の執筆はありますが、小説はこの「ザリガニの鳴くところ(Where the Crawdads Sing)」がデビュー作であり、現在のところ他には出版されていないようです。
映画と同じように2つの時間軸で語られていきます。
1969年、ノースカロライナの沼地で近くの町バークリー・コーヴに暮らす裕福な家庭の青年チェイスの死体が発見されます。沼地の鉄塔から墜落し途中の鉄骨に頭をぶつけたようです。鉄塔のまわりには足跡も残っておらず、何者かが足跡を消したと考えられ殺人事件として捜査が始まります。殺人だとしても物的証拠はほとんどなく、チェイスの衣服に付着した赤い糸とチェイスが始終身につけていた貝殻のペンダントがなくなっていることです。
湿地の少女と呼ばれてきた23歳の女性カイアが逮捕されます。赤い糸と同じ素材の帽子がカイアの湿地の小屋から発見され、また貝殻のペンダントがカイアが贈ったものであることが判明したからです。
湿地の少女カイア6歳1952年
6歳の少女カイアの家族、両親と5人の子どもたちはノースカロライナの湿地の小屋で暮らしています。とても文化的生活とは言えない環境で、それゆえに町の人々からは差別的な視線を投げつけられています。父親は第二次世界大戦のドイツ戦線で負傷し、その障害者手当をあてにする生活であり、妻や子どもたちに暴力をふるいます。
ある日、カイアは母親がトランクひとつを手にして何も言わずに家を出ていく姿を目撃します。そして3人の兄姉もいつの間にやらいなくなってしまいます。残された7歳ほど上の兄ジョディとカイア、しかし、そのジョディもカイアを残して去っていきます。
この母親や兄姉たちが去るあたりの描写はあっさりしたものです。父親の暴力の描写がありませんのでちょっと違和感を感じます。湿地にひとり残されたカイアの孤独が基本テーマですのでそこに絞られているのでしょうが、後にカイアが苦しむことになる、皆が自分から去っていくという感覚はひとりになったことよりも人が去っていくことを深く書かないとなかなか伝わりません。
とにかく、カイアと父だけの生活が1年ほど続き、その後、父が母からの手紙を読んだ以降は父もいつの間にか姿を消してしまいます。その時、父親は荒れて手紙や残された母の服なども燃やしてしまいますので、実際には何が書かれていたのかはわかりません。母親の消息も終盤になってジョディが戻ってきて母は亡くなったと語るだけです。上の3人の兄姉たちにいたっては何も語られません。
湿地の生活と少年テイト
カイアのサバイバル生活が始まります。一般的には無理だろうと思いますが、カイアは利発な子で母親がいた頃の記憶をたどってコーンブレッドを作り、母親と一緒に買物に行ったことがあるバークリー・コーヴに徒歩で買い物に行きます。父親がいる頃は、これで1週間分の食べ物を買えと1ドルとなにがしかのお金をくれており、また父親の機嫌のいいときにはボートで一緒に釣りに出たりということもあります。
ろくでもない父親でもいればお金をくれますので生きていけま・すが、いなくなればとたんに生活の糧がなくなってしまいます。10歳の頃です。救世主は町から離れたところに店を持っているジャンピンとメイベルの黒人の夫妻です。教会に寄付された衣服を与え、カイアが湿地で採った貝や燻製にした魚を買ってくれるようになります。
ある時、町から民生委員(のような人…)がやってきてカイアを学校へ連れていきます。しかし、皆から湿地の少女とバカにされ一日で行かなくなってしまいます。その後も幾度か民生委員がやってきますが、湿地帯を知り尽くしたカイアを見つけ出すことは出来ず、そのうち誰も来なくなります。
週に一度ジャンピンの店に行くのが唯一の人との交流です。湿地の植物や季節ごとにやってくる鳥や動物たちとともに生きるカイアです。はたから見れば美しくもみえますが、生活環境はともかくとしてもそのさみしさにはとても耐えられそうもありません。ただ、原文がどうかはわかりませんが、純文学ではありませんので記述そのものにずしんとくる孤独感が表現されているわけではありません。特異な設定に対する読むものの想像力が大きく影響する小説です。
10代の中ごろ、町の少年テイトと出会います。ある時、カイアは切り株の上に人の手によって鳥の羽根が置かれていることに気づきます。警戒するカイアですが、それが自分へのプレゼントと感じたカイアはお返しに違う羽を置いておきます。そしてテイトとの交流が始まります。テイトは兄ジョディの友だちだった少年であり、また、まだ幼かったカイアが初めてボートで湿地帯に出て迷った時に家まで誘導してくれた少年です。
テイトはカイアが読み書き出来ないことを知りやさしく教えてくれます。カイアは生来の賢さからみるみるうちに読み書きを覚えていきます。そして、時を経るうちに二人の間には愛がめばえていきます。キスする二人、さらに先へと進むのは自然の成り行きです。しかし、テイトはふっと手を止めてしまい、君はまだ15歳だと言います。
小説の中にはこのときのテイトの気持ちが書き込まれていませんので作者が何を考えていたのかはわかりませんが、これが現実であればテイトも怖かったのかも知れませんし、この後のテイトの行動を考えれば、テイトの真面目さを強調したかったのかも知れません。チェイスとは違うということです。
ただし、映画では別れの日にふたりは結ばれていました。原作にはその記述はありませんので映画の創作です。
テイトは大学への進学のために町を離れます。別れの日、テイトは必ず独立記念日に会いに帰ってくると言って去っていきます。しかし、約束のその日も次の日も、テイトが待ちわびるカイアの前に姿をあらわすことはありません。

映画からの画像ですが、いいシーンでした。切なさで涙がこぼれます。このことはカイアに深い傷を残します。みな自分の元から去っていくということです。母も兄姉も父も、そしてあれだけ約束したテイトまでもが自分の元から去っていき、自分はひとり残される身なのだと思い知らされます。
チェイスとの恋、なのだが…
そして、カイア18歳の頃、町の裕福な家の息子チェイスと知り合い付き合うようになります。
ただ、映画でもそうでしたが、原作でも、このチェイスという人物の人物像がどうもはっきりしません。どういうことかと言いますと、結果としてチェイスにとってはカイアは幾人もいる(らしい…)遊び相手のひとりに過ぎないわけですが、チェイスはカイアからの贈り物である貝殻のペンダントを肌身離さず身につけていたわけです。貝殻のペンダントですよ、人の価値観はそれぞれですが、これは小説ですので、あえて貝殻のペンダントであるからには意味があることですし、さらにチェイスは婚約し結婚した後もそのペンダントを肌身離さずつけていたわけです。一般的な物語であれば、そこには当然愛が介在していると考えるのが妥当です。なのにこの小説はチェイスのカイアに対する心情をほとんど深く語ろうとはしていません。
話が後先になりましたが、チェイスはカイアが幼い頃から目につく少年として顔を出しています。おそらく後半への振りだろうとは思いますが、付き合うことになる際にも、カイアの気持ちとしてはかなり積極的にチェイスを求める記述があります。チェイスが友人たちとビーチ(のようなところかな…)で遊んでいるシーンでは、カイアがチェイスをじっと見つめチェイスと目があうというような記述になっています。
チェイスが積極的に近づいてきます。カイアもそれにこたえます。カイアにとっては抱擁し合いキスをすることは人に触れることの喜びのような感覚だったのかも知れません。チェイスはさらに先に進もうとしますがカイアが拒みます。チェイスはごめんと謝ります。その後一年ほどそうした関係が続き、カイアも愛を感じるようになります。カイアは貝殻で作ったペンダントをチェイスに贈ります。チェイスが結婚をにおわせます。そして安モーテルで二人は結ばれます。その時カイアは、それまでチェイスの抱擁やキスに感じていたあたたかさを感じず、ただせっかちに自分の満足感だけを求めているように感じます。
やはりどうしてもチェイスの行動に感じる違和感が拭えません。下世話な言い方をすれば、チェイスはカイアとただやりたいがために一年間本心を隠してカイアの望むような付き合いをしてきたということになります。それなのにその日のためになぜわざわざ安モーテルへ連れて行ったのかも理解できません。私にはどうしてもチェイスが意志をもったひとりの人物として浮かび上がってきません。
まあこの小説はカイアの物語小説ですし、湿地帯でひとりで生きる女性という特異な設定で十分に想像力を掻き立てるだけの力がありますので、かえって、チェイスや、テイトもそうですが、他者についてはあまり深入りせずカイアの見た目や感じ方でいいのだとも言えます。
テイトとの再会と湿地研究者(のようなもの)への道
その頃、テイトも地元に戻っており、近くの研究所で働いています。カイアの初恋の人物であり、後に生涯をともに暮らすことになる相手なんですが、再会シーンもあまり印象的には書かれていません。
テイトは、チェイスが他の女性とも関係があることを知っていますので、カイアに忠告することが再会シーンになっています。当然、カイアは顔も見たくないと拒絶しますし、忠告を聞き入れることもありません。でも、なんとなくことは進展し(かなり曖昧に感じた…)、テイトはカイアが湿地帯の動植物について書い留めたものを見て、これは本として出版すべきだと考え、出版社に送ってみることを提案します。
その後、出版は実現し、カイアには印税が入ることになり、さらに湿地帯一体がカイアの祖父の所有であることがわかり、税金の滞納分を支払うことでカイアの所有となります。
同じ頃、カイアはジャンピンの店で目にした新聞記事でチェイスが婚約したことを知ります。動揺するカイア、騙されたとの気持ちとともにこれまで幾度も感じてきた皆自分から去っていってしまうという孤独感に襲われます。
ある日、チェイスがボートでやってきます。それまでカイアは身を隠して避けていたんですが、その日は捕まってしまいレイプされそうになります。
このレイプ未遂もちょっと違和感があります。チェイスはその後もつきまといますし、後の裁判でこのレイプ未遂の目撃者が証人として出廷しますのでそのためのものなんだろうと思います。実際、チェイスがカイアとやりたいがためだけにつきまとっているというのは、他にも多くの女性と付き合いがあるという設定から考えますとなんとも不自然です。
なぜこんなにチェイスにこだわっているのか自分でもよくわかりませんが(笑)、あらためて考えてみますと、チェイスにもカイアへの愛があったとしておいたほうがよかったんじゃないかということです。婚約の件はその時代であれば親の望みに従ったことで理由がつくでしょう。そうすれば始終ペンダントを身に着けていたことも、一年カイアの希望を尊重したことも自然になります。まあ余計なことではあります(笑)。
逮捕、裁判、そして…
長くなってしまいましたので簡潔にいきます。
カイアが逮捕されます。
起訴は状況証拠だけですので、検事と弁護士がひとつの証拠や証人に対して異なった見方を提示し正反対の結論を導くというとてもおもしろい裁判になっています。裁判にはテイトやジャンピンとメイベル夫妻、それにカイアの出版物を見てもしやと思い訪ねてきたジョディも傍聴しています。
裁判は陪審員裁判です。カイアに無罪が言い渡されます。
裁判中にも町の人々のカイアへの偏見が記述されていますので判決への影響はどうなんだろうと思いますが、そうしたことへの記述はなく、判決後は一章あるくらいであっさりしています。
カイアとテイトはカイアが64歳で亡くなるまで湿地帯の小屋(改装されている…)でともに暮らすことになります。そして、カイアの死後、テイトはカイアが生前アマンダ・ハミルトンの名前で新聞に詩を投稿していたことを知ります。その詩はカイアがよく口ずさんでいたものです。
そして、その詩が収められた箱の中には貝殻のペンダントが隠されていたのです。
映画ではアマンダ・ハミルトン名の詩に関してはカットされており、ペンダントはカイアが書いたの本の中が切り抜かれて隠されていました。詩の投稿というのはちょっとやり過ぎな感じですので映画の選択は妥当かと思います。
物語小説として読めば面白い
文芸作品、あるいは純文学としてとらえますと、プロットに雑な面もありますし、人物描写も物足りなく感じます。いろいろ書いてきたチェイスのこともありますが、家族への記述がほとんどないのはカイアの孤独を強調する上もマイナスに感じます。それに翻訳の文章、特に会話文の稚拙さが気になります。
とは言っても、とにかく設定が特異ですのでそれだけでも面白く読める小説です。
ところで「ザリガニの鳴くところ」の意味ですが、カイアがテイトに意味を尋ねるところがあり、テイトは「そんなに難しい意味はないよ。茂みの奥深く、生き物たちが自然のままの姿で生きてる場所ってことさ」と答えています。
なんだか納得がいかないですね(笑)。ザリガニって鳴かないでしょう。それも sing ですよ。ありえない場所ってことじゃないんでしょうかね。映画のレビューでは、わたしは次のように書いています。
で、「ザリガニが鳴くところ(Where the Crawdads Sing)」の意味です。これが正しいのかどうかは原作を読まないとわかりませんが、カイアが母親から「ザリガニが鳴くところまで行きなさい」と言われていたと語っていたのは、「Go as far as you can -– way out yonder where the crawdads sing.」ということで、つまり、そもそもザリガニは鳴かないわけですから、鳴くところというのは現実には存在しないところまで行きなさいということで、そこにはいろいろな意味が含まれているんだと思います。
人間が失ってきた野生といった意味があるかもしれませんし、映画的に言えば、人間社会から逃げなさい、さらに現実的な意味で言えば、男たちの暴力や社会の見えざる暴力から逃げなさいということも含まれているのかもしれません。
(ザリガニの鳴くところ)